子どもはみんな3匹のタイを飼っている?
先日、日本サッカー協会(以下JFA)が主催する研修会や都道府県協会(以下FA)が主催するインストラクター研修会に参加して参りました。
JFAの担当者の解説では、暴力根絶の動きはあるものの、なかなか広まっていかないとのことでした。
2013年から設置した暴力根絶相談窓口も、相談件数が減ることがないのが現状です。

今回はネガティブなニュースを取り上げるのではなく、どうすれば、子どもたちを笑顔にできるのか?を考えてみたいと思います。
話の中では、「どの子の心にも3匹のタイが泳いでいる」というトピックスがありました。
- ほめられタイ
- 認められタイ
- 愛されタイ
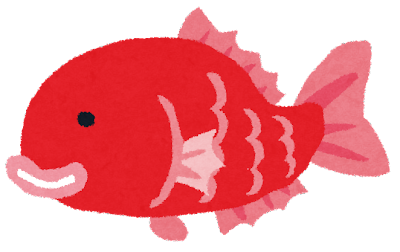
言わずもがな、これは子どもに限った話ではないのですが、いざ、サッカーやスポーツをしている子どもに対しては、こういった意識を大人が持っていない、あるいは、持ちにくくなっているのではないかと思わされます。
だから
- もっと褒めてあげましょう
具体的に、タイムリーに、みんなの前で - もっと認めてあげましょう
存在を、ありのままを、隠れた努力を - もっと愛してあげましょう
失敗も、素直になれない心も、そのままを
具体的な方法は?
今日は【メラビアンの法則】をヒントに、工夫をしていきたいと思います。
メラビアンの法則とは、コミュニケーションを図る際に、相手に与える影響のことです。
- 視覚情報 55%
- 聴覚情報 38%
- 言語情報 7%
コミュニケーションを取る際は、話の中身が大事だと思われがちですが、実際には言語情報は7%しか優先されず、視覚と聴覚から得る(与える)情報、非言語的コミュニケーションが93%も優先されるというものです。
ここで大事なことは、日常的なコミュニケーションに常にこの割合が適用される訳ではなく、この法則を拡大解釈して、話の内容を無視することがあってはいけないということです。
非言語的コミュニケーションと同様に、言語的コミュニケーションも重要だという理解は必要です。
その上で、大きな身振り手振りやジェスチャーを入れて視覚情報に訴えかけると、より子どもに熱意が伝わるかも知れません。抑揚もつけず、淡々と話されても保護者や指導者の愛は伝わりません。褒めるときはオーバーなくらいでちょうど良いのです。そして、笑顔を忘れないことです。威厳を出そうとして、無表情で褒めていては、子どもは躍動しません。
少しずつ意識して指導や子どもとのコミュニケーションに活かしてください。



コメント